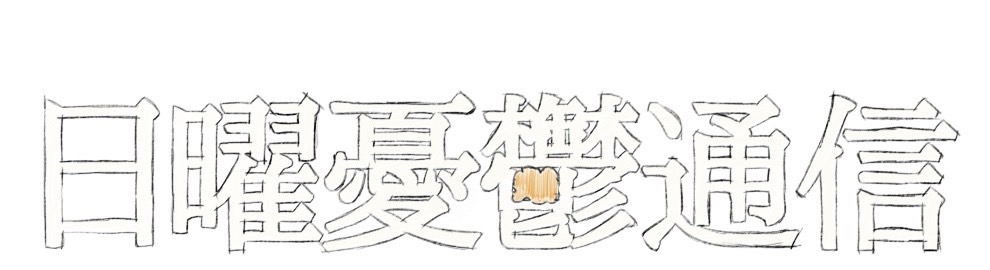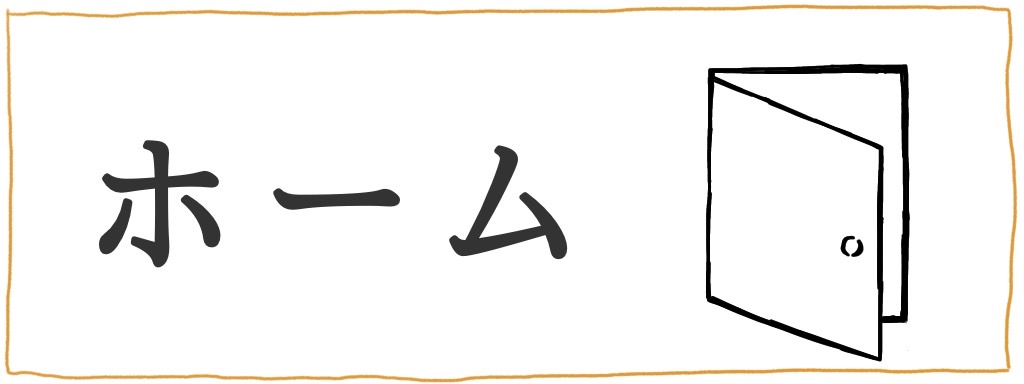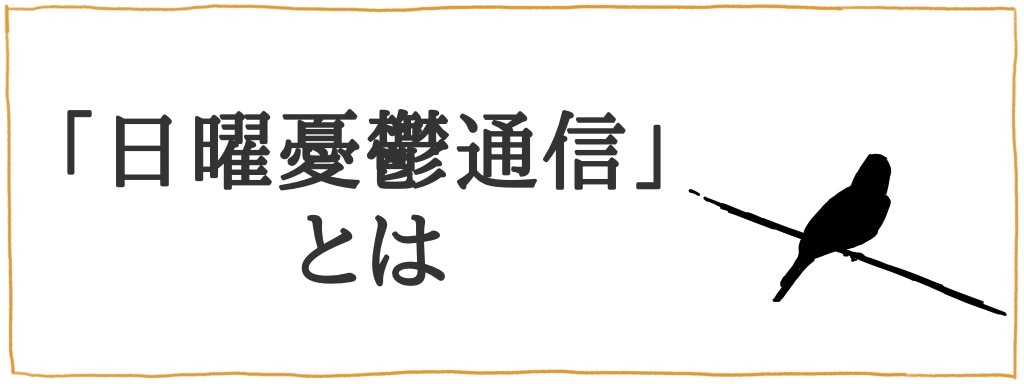「今年は絶対令和ロマンが優勝するよ」
長谷川凛はそう言うと、座席から立ち上がってつり革を掴んだ。車窓を流れていた午後の田園風景は、彼女の制服に隠れて見えなくなった。
「えー、やっぱ行っちゃうのかなぁ。去年敗復2位だもんね」
そう言い返したのは伊村園子。私の隣に座っている。彼女はさっきNewDaysで買ったヨーグリーナをグビグビと飲み干すと、「でもまだ若手でしょ? さすがに早いんじゃないかなー。えーでもやっぱ行っちゃうのかなぁ」とそのままの勢いで続けた。彼女の声は少し高くて、電車の中でもよく聞こえる。園子は両足で挟んで置いていたリュックを開けて空のペットボトルを入れると、
「千遥ちゃんは? どこが優勝すると予想?」
と聞いてきた。少しだけ開いたリュックから、白いタオルが覗いていた。
私は何となくそのタオルを見つめながら、頭を徐々に回転させていく。私としては、フースーヤが決勝に進んでくれれば何も思い残すことはない。あのスタイルのまま決勝に上がったら私は飛び跳ねて喜ぶんだけど、優勝するとなると話は違う。フースーヤが優勝してしまったら、それは私の望む大会じゃない。こんなに好きなのに優勝して欲しくないなんて可笑しい話で、やっぱりお笑いはスポーツではないのだと再確認する。
今年の優勝。凛は令和ロマンのファンだが、私は決勝に行くような(少なくとも9月の時点で決勝に行くだろうと容易に名前が挙がるような)コンビは正直あまり興味がない。だから私はお笑い好きとしてではなく、棒グラフを指しながらニュースを解説する専門家のような気持ちで、
「さや香」
と答えた。
気づけば園子も立ち上がっていて、私は誰も居ない小豆色のシートを見つめていた。
「さや香かぁー。やっぱそうだよね。私も去年は行くと思ったもんなぁー」
園子は車内がどれほど空いていても、電車では絶対にリュックを前に掛ける。でも何故か、つり革は掴まない。
「えー。でもさ、あの2人、仲悪いんでしょ?」
「悪い。けど私は別に好きだな。最近のお笑い界は仲良しアピール必死すぎ」
凛は網棚から三脚を下ろしながらそう言うと、
「それと、千遥に優勝予想なんて聞いても意味ないよ。この人はフースーヤしか応援してないんだから」
「あー、そっか! そうだよね」
「いや、そんなことないから!」
「私、千遥の筆箱から田中ショータイムのアクスタが見えたとき悪夢かと思った」
「あー、あったね! それ!」
「だから、あれは部活の時2人に見せようと思って入れてたってだけで! まさか昼休みに2人が来ると思ってなかったから!」
「だからって筆箱に入れないでしょ普通。妖精かよ」
「ははは! 学校に無理矢理ついてきちゃった妖精でしょ?」
電車は停車し、目的の駅に到着した。私は立ち上がりリュックを背負う。教科書ノート参考書で肥大化したこのリュックを背負うたび、将来の不安を思い出す。
とりあえずね、と呟いて、園子は駅の写真を撮影した。もう何年もペンキを塗り直していなさそうな、白い外壁の無人駅。入り口に掛けられた「入堵駅」の看板がなければ、駅だと気づかないまま通り過ぎてしまいそうだ。
「電波あるー?」
首からぶら下げたデジカメを揺らしながら、園子が振り返った。凛がスマホのロック画面を見て
「3G。あって無いようなもん」
とだけ報告する。
私たちが高校からはるばるこの入堵駅にやって来た理由はただ1つ。とある中華料理屋さんへ行くためだ。といっても、ただお腹いっぱいご飯を食べるだけの食いしん坊ではない。一応、名目はある。「取材」という名目。私たち3人は新聞部だ。
今月末に発行する新聞に、入堵駅付近にある町中華「永々亭」の食レポ記事を書きたいのだ。これといったネタが無くて困っている中、園子が夕方の情報番組で永々亭の大盛りメニューが紹介されているのを大目撃した。新聞を作る、なんて活動にこれといった活力を沸かせることの出来ないまま、たまたま部員全員がお笑い好きであるという煤けた不運も重なって「お笑い厄介オタク部」と化していた新聞部。
そんな状況下でグループLINEに投下された「堅焼きソバ(大)」の写真はまるで豪族の墓を下から見上げたみたいで、私と凛の興味を一瞬で惹きつけた。
「そういや自分の胃のキャパ分からん」「確かめる価値はある」「ギャル曽根の凄さを身をもって知る経験も必要」「人が大食いをしてるのを観るって文化、何?」
このような意見がやる気に拍車をかけ、私たちとしては珍しく一週間前に電話で取材交渉をし、今日腹をすかせてやって来た。褒められるべきだと感じる。
「千遥ー。千遥を地図担当に任命します」
「まって、私充電ないかも」
制服のポケットからスマホを取り出す。Twitterで見つけたフースーヤのイラスト(「カギカッコみたいだねっ!」の場面)の右上に、カッスカスの3%。
「3%でーす」
「なんで?」
「充電しようとか思わないの?」
地図係は凛になった。ラグまみれのGoogleマップで経路案内をスタートさせる。まだ夕方にはなっていないが、夜になると街灯もないので真っ暗だろう。
「あ、自販機。ジュース買って良い?」
先ほどヨーグリーナを飲み干した園子が真っ先に財布を取り出す。私も喉が渇いた。今から確実に大食いをするのだからせめてウーロン茶を買おうとポケットに手をつっこむと、
「あれっ」
財布が無い。
すぐさまリュックを降ろして中を探っていると、
「絶対に財布をなくしてる人がいるねー」
と、財布をなくしていない園子が笑った。私も力なく「いやー、ははは……」と笑う。
「電車の座席にはなかったよ。トイレは?」
凛が「またかコイツ」と言っているも同然な冷めた口調で言う。そうだ、私は改札を出た後に一旦トイレへ行った。
「ごめん見てくる! 先行ってて!」
そう言い残して、リュックを背負って急いで走る。
「ファイトー」
後ろから2人の声。
短時間で同じトイレに2回入るときの心境は、なんとも小っ恥ずかしい。駅舎から少し離れたところにあるトイレは、どういう当番制かは知らないが掃除が行き届いている。
そしてこれまたどういうわけかは知らないが、数分前の私はトイレットペーパーホルダーの上に財布を置きっぱなしにしたままなのであった。
こういうヒヤリハットを起こす度、財布のあまりの貴重品さに恐ろしくなる。これを無くしたら、現金も、学生証も、Suicaも、全てが無くなる。……高校生の財布の中身なんて大したことないが。あ、でもお守りも入ってるから、やっぱり貴重。
トイレから出ると、駅の前には誰も居なかった。先に出発したのだろう。ほんの1分くらいしか経っていないだろうから、2人はまだ近くにいるはずだけど、
「……あれっ」
いない。辺りを見回しても、人影すらない。まぁ、歩くスピードが速い人達ではあるのだが。
スマホを取り出す。
「えっ! ちょっと!」
カメラが起動されていた。さっきポケットにしまうとき、ロック画面をスライドさせてしまったのだろうか。しばらくの間起動されていたカメラアプリはスマホの貧弱なバッテリーを食い漁り、
「あ」
画面が真っ暗になった。
「………………」
仕方なく息を吸う。山の匂いがする。
充電無し。永々亭の場所も知らない。2人も見当たらない。どっち方向に行ったのかも。
入堵駅。
詰み。
「……ははは」
どうしよう、これは全然笑えない。
(中編へ続く〜)
中編はこちら!