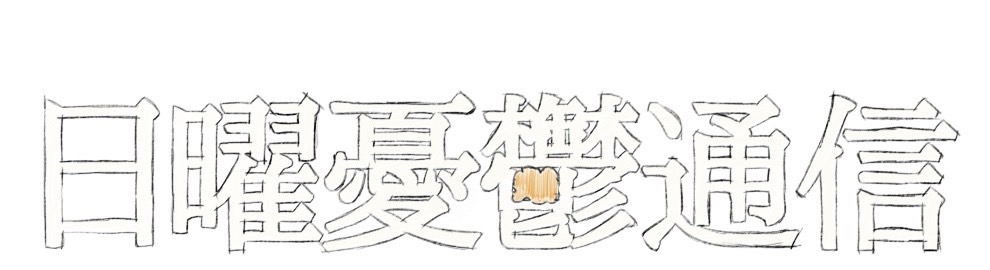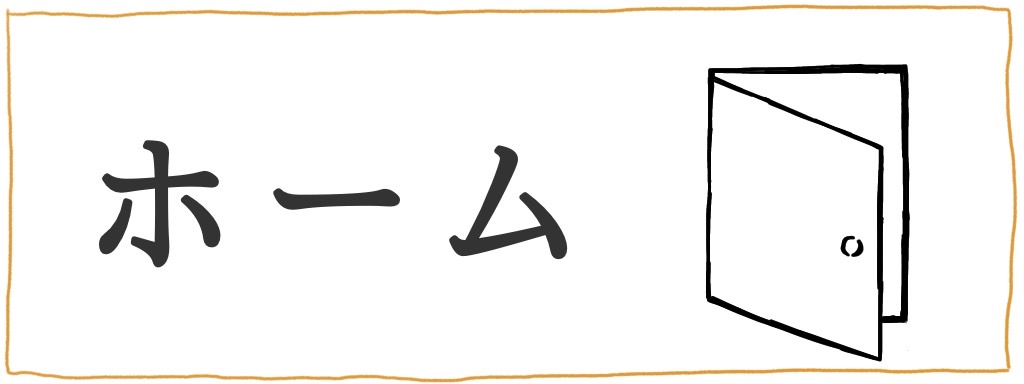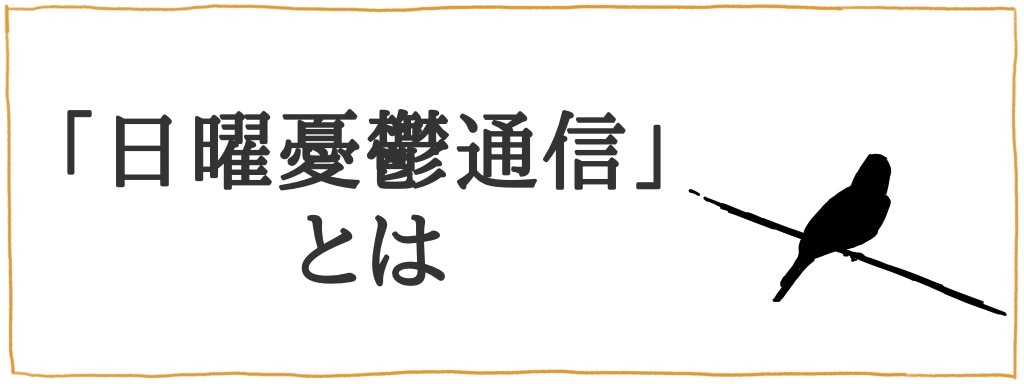中編はこちら!
生き物みたいな水だった。右手についた水滴をはらい、目の前に広がる海のような湖を見つめる。
私は、湖というものについてよく知らない。現時点まで私が持っていた湖のイメージなんて、「でっかい池」。ただそれだけ。だから、イオンモール数個分ほどもありそうなサイズのこの湖に砂浜があって、波があって、防波堤もあって、カモメも飛んでいて、漁船もとまっていることが果たして普通のことなのかどうか、私には全く分からないのだ。
おっきい湖って、みんなこうなの?
またカモメの鳴き声だ。マックで騒ぐ女子高生の声みたく、それは私の遠くで鳴り響いた。こんなにカモメが喜々としているものなのだろうか、湖って。
でもただ1つ、私でも「明らかにおかしい」と気づくことがある。
磯の香りがするのだ。砂に混じってしょっぱさが鼻をさすような香り。この香りって海だけのもののはず。
この湖は、なんなのだろう?
だがそんな疑心も、波の音がかき消してしまう。海という場所が持っている、「細かいことをどうでもよくさせる」効果が私の脳味噌にも十二分に働いた。気づけば浜辺の砂を踏みしめたときのモキュッとした感覚に酔いしれていて、靴底越しに足裏へ届く細かな貝殻の輪郭を感じながら、「海って良いなぁ」なんてありふれたことを思っていた。
突然、視界に黄色い異物が入った。ボールだった。湿った砂をごま団子のように表面に纏いながら、黄色いビニールボールが転がって、私の前で止まった。「すみませーん」
人の声を聞いたのは、私が財布を取りにトイレへ走った際に園子と凛が言った「ファイトー」以来だった。ビクッと跳ねた身体を勢いそのままに声のした方向へ向けると、少し離れた場所に、幼稚園生くらいの男の子と、その母親と思わしき女性がいた。女性は長い茶髪が風になびくのを手で必死に抑えながら、
「すみません」
とまた言った。その顔は笑っている。
あぁ、これはよくドラマで見るやつだ。子供が飛ばしたボールを拾って、返してあげるやりとり。人はこの些細なコミュニケーションの中に、どういうわけか自分の心がふっと軽くなるような「純粋への浄化作用」のようなものを見いだす。ここで子供にブチ切れる登場人物など存在しない。
私はそのごま団子のようになったボールを拾い上げて、母親から離れてぽつんと立っている男の子の方へ歩いた。でもその子は一切動かず、突っ立ったまま私の目を見つめている。
「投げて」
母親の声だった。両手を下から振り上げているのは、ボールを投げるジェスチャーだろう。わざわざ渡し方を指定する理由が分からないが、私は言われたとおりにボールを投げた。空中に浮かんだボールは何粒かの砂を飛ばし、その砂は太陽の光を反射してキラキラ光った。
「ありがとうございますー!」
ボールは大きな弧を描き、男の子の両手にふわりとおさまった。彼が両手でしっかりとボールをキャッチしたを見て、そういえば私は、少しでも手に砂がつかないように指先でボールを掴んだことを思い出した。ほんの数秒前の私の行動が、子供の頃に持っていた「手がどろんこになるのを気にせず遊ぶ」という純粋性を排除したものなのだ。
私は大人になってしまったのだろうか。手に砂が付くのが嫌になったのは、いつからだろう。子供と海に挟まれた私は、ぷかぷか宙に漂うように、そんなことを考えた。
波の音って、良い。波の音がバックにあると、いつの間にか私も情緒が豊かになって、地球が鳴らすリズムと一体となって呼吸をしている気がする。もし、波の音が常に聞こえる環境で生活をしていたら、私の思春期はどう変わり、どんな人間に成長していたのだろうか。堤防の上をバランスをとって歩きながら、そんなことを考えた。
堤防は浜辺と道路の間に境界線を引くように伸びている。その上を歩く私は、制服を着て、まるで映画の主人公になった気分だ。どんな映画かっていうのは良く分からないけど、雰囲気として似てるのは……アクエリアスのCM。
「どこから来たの?」
「えっ」
反射的に声を出してしまった。下を見ると、男の人が堤防に寄りかかって本を読んでおり、私の足元に彼の肩があって、そのまま歩いていたら頭を蹴っ飛ばしてしまうところだった。
「ここら辺じゃ見ない制服だからさ」
彼は顔を上げ、私と目を合わせた。ワイシャツに赤いネクタイを締めている。私と同じ、高校生だ。隣には自転車も停めてある。
男子と目を合わせるのは久しぶりだ。学校ではほとんど異性と話さない。でも私は、
「そう?」
と、何の抵抗もないかのように、慣れっこのように、答えた。
「どこからでも良いじゃん。遠くから来たんだ」
不思議だ。この町にいると何故だか気分が嬉しくなって、こんな台詞じみたことを言ってしまう。まるで飼い猫のお腹を猫じゃらしでくすぐるように、私はこの地球と触れ合いたい気分なのだ。
「そうなんだ。何しにここへ?」
「永々亭っていうお店を探してるんだ。中華料理屋さんなんだけど」
永々亭という単語が久しぶりに思えて、自分で言いつつ笑いそうになってしまった。
「永々亭……」
彼は本を閉じて虚空を見つめた。
「知らないなぁ。この町のお店じゃないのかも」
彼の声はほどよくざらついていて、耳を通るのが気持ちいい。私は堤防に腰掛け、そしてひょいっと地面に下りた。私は入堵駅から出る際の2択をミスったのだ。いっつもそうだ。
「そうなんだ、ありがと」
私はそう言って、ちょっと歩いて振り返って、
「じゃあね」
と彼に言った。
この町はどこか浮き足が立っているようだ。その証拠として、烏龍茶を買おうと思って立ち寄った自販機のラインナップ。
コカコーラ、コカコーラゼロ、ファンタグレープ。アクエリアス、ポカリスエット。ビタミン炭酸マッチ、メローイエロー。カルピスウォーター、がぶ飲みメロンソーダ……。
お茶なんて無かった。何となく痩せそうだからという理由で烏龍茶にこだわっている私の居場所は無かった。
ふと横にあった看板を見ると、ざっくりと描かれた文字の上に「いりと青春区画」とあった。強い日差しをしょっちゅう浴びているからか、看板の表面は日焼けで色が薄くなっている。
仕方なく、というか丁度飲みたい気分だったのでアクエリアスを買うと、後ろで自転車のベルが聞こえた。振り返るとそこには、さっきの男子高校生が立っていた。
「永々亭、だっけ? 思い当たる場所が1つあったんだ。乗りなよ」
彼は自転車の荷台を見やった。
男子の自転車の荷台に乗る女子高生。それに、そのキラキラした存在に、なれる。私が。
銀色に光る荷台を見つめる。蝉が鳴いていることに気がついた。
「いいの?」
私は答えた。
(後編②へ続きます! 多分次が最後)