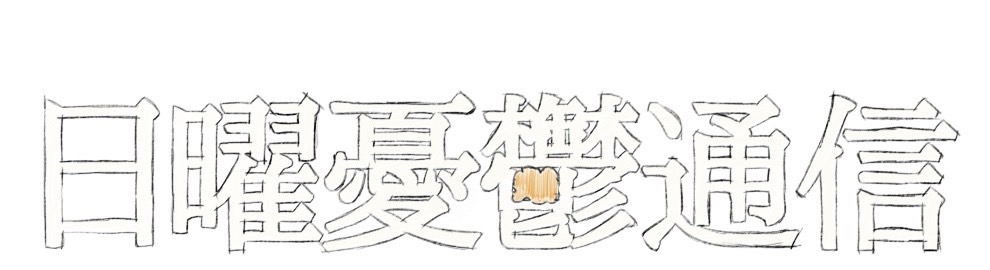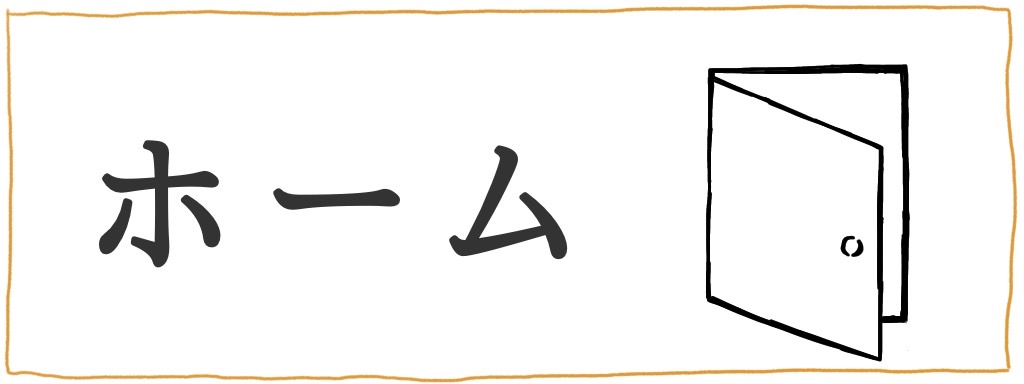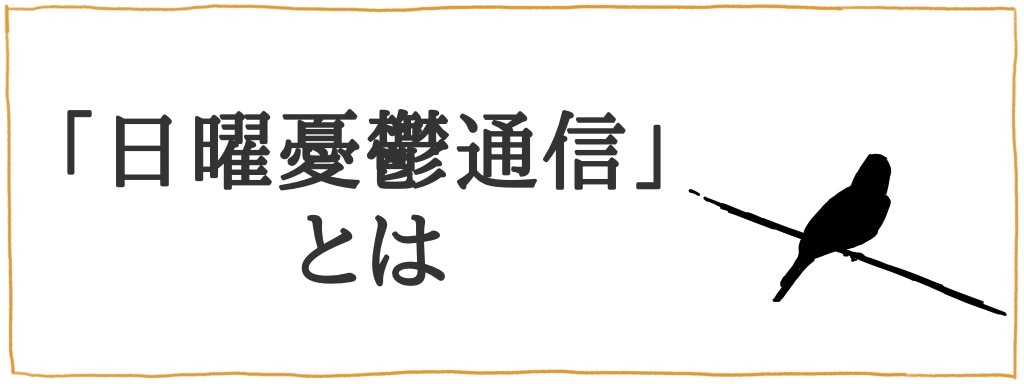空気が地続きだなんて、俺は信じていない。
今まで様々な現場に入ってきたが、そのどれも違った空気を纏っていた。雑居ビルには雑居ビルなりの埃っぽい空気があり、長年人が住んだ民家の空気は住人の吐いた息が残っている気がする。ありふれたコンビニにさえも、コンビニの空気というのはある。
神社の鳥居をくぐったとき、確実に周りの空気は変わる。科学的にはそんなこと無いはずだが、感覚はそれを否定しない。これは恐らく、鳥居をくぐった瞬間に人間の意識が切り替わるから、だから空気が変わったように感じるというだけの話。空気というのは、所詮は自らの主観が作り上げた「思い込み」に過ぎない。雑居ビルも民家もコンビニも。
そしてこの場所も。
母校の中学校を解体する話を聞いたときの感覚は、「月日の経過」という凡庸な表現では言い表せず、生々しく胸にズシンと落ちるものだった。解体工事の仕事に就いてから12年。これほど思い入れの強い現場は無い。「思い入れ」という言葉を使うのは癪に障る気もするが。まぁ詳細はどうであれ、一応3年間はこの校舎で過ごしたのだ。浸る感傷は曲がりなりにもある。
作業が開始してから3週間。ここの空気には慣れない。中学校の空気。中学時代の空気。ジメジメしていて、窮屈で、薄暗くて。残念ながら、俺が当時味わっていたものが当時の鮮度を守ってしっかり保存されていた。毒ガス同然のこの空気を吸うと、俺はたちまち丈の足りなくなった学生服を着て、自分を守ることに必死だった中学時代にタイムスリップしてしまうのだ。なんだか情けない気分になってしまう。
校舎内の撤去作業は既に完了しており、残す行程は建物を壊すだけだ。(一応、校庭に生えている樹木を伐採する作業もあるにはあるが、まあいい。)外の地面から眺めるすっからかんの校舎は、なんだか魂が抜けているようで軽い。3階建ての校舎は全てのガラスが外されており、20年前は青空を眩しく反射させていた窓の部分は、暗く閑散とした校舎内を覗かせるだけの穴と化していた。ふと、骨粗しょう症になった骨の断面図を思い出した。あの画像も、たしか中学の保険の授業で見たんだ。俺の骨は大丈夫だろうか……。
目の前に見えているのは、かつて職員室だった部屋だ。奥の柱に取り付けられた緑のボードは、何となく覚えている。確か、各学年の学年だよりが掲示されていたはずだ。あそこに貼られるやつだけカラー印刷だったんだよな。
物質が全て剥がされた校舎には、記憶だけが空気に溶けて漂っていた。何もない分、非物質的な要素が余計に際立つ。窓が全て外された空間には開放感が生まれているはずなのに、閉塞感しか感じない。あの頃のままの。これが学校の空気か。そうだそうだ。これだ。
「それでは、今日の注意事項を確認します」
昇降口の前、まるで集会のときの校長先生みたいに、現場監督の平山さんが朝礼を進行している。白い息を吐き、メガネを曇らせる。その話を聞いている俺たち作業員も、これまた先生の話を聞く生徒のように整列しているのだが、グレーの作業服を着た大人達が校庭に並んでいる様子はまるで学校が乗っ取られたみたいで愉快だ。敷地の四方に高さ3mの仮囲いを並べ、ザリガニのハサミのような圧搾機を取り付けたパワーショベルを待機させた、白いヘルメットの男達。今から目の前の校舎をぶっ壊す仕事に取りかかる俺たちは、この学校の生徒が見たら悪者にでも映るのだろうか。平山さんは悪の組織のリーダーだ。
「では、準備体操に入ります」
太っているのに声が高いから、そうは見えないか。朝礼は準備体操に移った。体格のいい男達が行儀よく腕を回したり屈伸をしたりする姿はまるでオモチャみたいで、俺は毎回吹き出しそうになってしまう。一体どの筋肉をほぐしているのか本人たちも分かっていないテキトーな運動が終われば、長い1日が始まる。
長い1日。ただ今日は、口を伝ってマスクの中に広がる吐息の温度が違う。何故なら今日は、母校をぶっ壊す日。俺が操縦するハイリフト油圧式ショベルカーで、俺の中学時代をぶっ壊す日。
「黄金の3日間って知ってます?」
体育祭が終わったあと、廃業したガソリンスタンドの横にある踏切を渡っていたときのことだ。家が近い、という理由だけで毎日一緒に下校していた塚田、が勢いよく発したのだった。
「……なにそれ」
「お兄ちゃんから聞いたんですけど、学校の先生って、クラスの構造を始業式からの3日間で決めるんですって」
青いジャージの俺たちを、小学生の集団下校の列がさっさと追い抜かした。気づけば空は夕焼けで、その日1番のオレンジ色だった。
「最初の3日間で、先生は全部に気づかなきゃいけないんです。このクラスで誰が中心になるか、誰がパワーを持ってて、誰が持ってないのか。無視される奴は誰で、無視されない奴は誰か」
担任の先生の顔を思い浮かべる。和田先生。普段は少し怖いけど、話が面白くてみんなから好かれている。
みんなから好かれている。
「で、3日間で、そっから1年続く構造をつくるんです。パワーを持ってる奴と話して、仲良くなって、結果的に先生もパワーを持つんです。3日間でそれができないと、先生はなめられて、その学級は上手くいかないんです」
「だから、結局は全部先生が決めてるんですよ。クラスの中心とか、何をやっても許される人とか、こいつは目立っちゃいけないっていう雰囲気とか。全部」
学校から1番近い無人駅の駐車場に軽トラックが1台停まっていて、中で紺色のキャップを被ったおじさんが寝ているのが見えた。
「僕と先輩が教室で居心地悪いのだって、先生が決めたんですよ」
リクライニングの出来ない狭い座席で、ハンドルにうつ伏せになって音を出さずに寝ていた。
「どう思います?」
歩くうちにそのトラックは視界から外れて見えなくなって、また夕焼け空が広がった。稲藁の香りがした。
「なにが?」
「黄金の3日間」
…………。
「きめェ」
「はいっ?」
目の前にいたのは平山さんだった。
「いやあの、だから、ハイリフトの方、安全第一でお願いします」
「あぁっ、了解です!」
中学時代の景色が途切れ、コップに水を注ぐように現在の景色に置き換えられていく。安全第一の確認を聞きそびれるなんて、回想ってのはろくなもんではない。
「いやぁ。この仕事に就いて長く経ちますけど、こんな働きがいのある現場はないですよ」
俺はいかにも現場の男らしく、声質から腕の筋肉の隆々しさまでも伝わるようなハッキリとした言い方で言った。だが平山さんは、
「そうですか」
と一言だけ言って、テディベアのような巨体をくるっと回してトコトコ歩いて行ってしまった。彼と同じ現場を担当することはこれまで幾度となくあったが、距離を縮めている手応えは一切ない。彼が今までどんな日常を送ってきたのか。例えば、普段はどんな音楽を聴いているのか。そういった彼の境界面から踏み入ったことは、職場の人間の誰も知らない。
年間スケジュールに母校の解体を発見してから、胸がぞわぞわした感覚が続いていた。この中学が廃校になったのは、もう3年ほど前になる。正確には、周辺の数校と「統合」されて別の校舎に移ったのだが、子供の数が少なくなっている現状を伝えていることには変わりない。小学校の廃校はまだ聞く話だが、中学校となるとちょっと笑えない。老いた脳を振り絞って考えた数々の町おこしの健闘空しく、地方の少子高齢化がいよいよここまで来てしまったか。何というか、自分の死期を悟るような。しっかりと前を向いてバッドエンド確定の未来を見据えなければいけないという、少々過酷な現状だ。
ただこの胸のざわめきは、そんな地方消滅云々のような広くて薄いスケールの話ではない。もっと狭くて濃い、個のスケールの話だ。俺がいまから解体するのは、単なるコンクリート造りの建物ではない。忌々しくもこの建物に内包された中学時代の記憶、すなわち「空気」の全て。俺は空気を解体する。あの頃、教室内の全てが吸って、読んで、従っていた空気を解体するのだ。
そうしたらきっと、俺は果てしなく清々とした気分になれるはずなのだ。しょっちゅう靴紐が解けていた靴を脱ぎ捨てそのまま裸足で道路を歩いて行くような、そんな優しい気分が満ちあふれるはずなのだ。
ハイリフトの操縦席に乗り込み、右手で安全レバーを下げる。いわゆる「工事現場の音」の発生源に身を包み、フロントガラスに覆い被さるように装着された鉄柵の向こうに校舎を眺める。この鉄柵は、瓦礫がガラスを傷つけてしまうのを防ぐ役割を持っている。俺は安全圏にいる。
「放水お願いします!」
平山さんの指示を合図に、視界の左端から水しぶきが上がった。圧搾機で外壁を破壊する際に粉塵が巻き散るのを防ぐために、解体と同時に放水を行うのだ。晴れているのにびしょ濡れになっている姿は新鮮だ。教室の中に水が入ってもお構いなしな様子を見ると、本当にこの中学校の中には誰もいないことを実感する。
右手のレバーを下げ、ショベルが錆び付いた轟音を鳴らして持ち上がる。先端の圧搾機が開き、2階のベランダ部分に狙いを定める。
俺は今から怪獣になって、この学校、教室、空気、全てを破壊する。
はじまる。
チャイムが鳴った。
「全校生徒の皆さんへ連絡します。担任の先生の指示に従って、今すぐ避難を開始してください」
どの先生の声かも忘れた。だが聞き慣れた声だ。俺は窓ガラスを割り、教室の中へハサミを突き刺した。カーテンが大きくたなびいて、ビリヤードの球みたいに机の大群が波を打って蹴散らされていく。金属音のような叫び声で、数人の女子生徒が廊下を走っていくのが見えた。懐かしいな、あの制服。
ハサミを一旦外へ抜いて、今度はベランダの外壁を挟む。ボコボコッとコンクリートが土塊のように崩れ落ち、一緒にエアコンの室外機と、誰かの上履きと、干してあったクラスの雑巾が落っこちてきた。授業中の教室に大きな穴を開けると、黒板消しクリーナーが転げ落ち、白いチョークの粉が舞った。火事現場のような白煙を、放水で落ち着かせる。
同じ場所をまたハサミで攻撃する。鉄筋がむき出しになり、そこを何度も執拗に攻撃する。 何度も、何度も。
少しずつ。粛々と。安全第一で。
……怪獣か? これ。
怪獣じゃあ、ないよなあ。こんな地味に建物を壊す怪獣、いないよな。もっと破片が巻き散るように、バゴーンっていくよな、普通。
リンゴを囓るように、少しずつ校舎が削れていく。もうとっくに生徒は避難をして、けが人を出すことも無く校庭に集合している。いや、もはや避難すらしていなくて、臨時休校の指示に従ってみんな家で寝ている。それかもう大人になって、こんな限界の田舎から遠く離れた都市部で仕事をしている。家庭を持っている。
そうだ、そうじゃないか。まだここ残っているのは、俺だけだ。俺だけが避難指示すら聞こえずに、窓際の机でうつ伏せになって寝たふりをしているんだ。
粛々と、細かくやっていく。
思えば、モノが壊れるときはいつもこうだった。一気に大破なんてことはなく、ちまちまと負担をかけているうちに、少しずつ削れて壊れていく。人生だって、心配の無かった日々だって、こういう風に壊れていく。
どこまでも安全な行程が踏まれた上で、怪獣の俺は、迫力皆無の世界で思い出を壊していく。
「きめェ」
あの時、夕焼け空に中指を立てるような思いで放った一言が、あの頃のまま目の前の空気を漂っている。
そうか、きめェよな、自分が。
教室の中、寝ている俺がいる。外界全てを拒んだつもりで、本当は喉から手が出るほど欲しがっている強がりな俺が、ダンゴムシのように机でうつ伏せになっている。
どうせまた寝たふりだろ。気づいてるんだよ俺は。
俺は圧搾機で俺の胸をはさみ、そのまま天高く持ち上げた。天井と屋上とを立て続けにぶっ壊しながら、学生服の俺が放水で濡らされる。ハイリフトを最大限まで伸ばし、地上8階建ての高さにまで俺が持ち上がる。
俺が壊したかったのは学校ではない。あの頃の俺だ。
勝手に「空気」を感じていた、俺自身。その凝り固まった自意識と価値観を、この歳になっていよいよ壊したくなった。
血だらけで天高く持ち上げられている中学の頃の俺を眺めると、無駄だったんだなぁと思う。俺はレバーを一気に奥に倒し、俺を外壁に叩きつけた。放水があるから粉塵は飛ばなかった。
「今日もお疲れ様でした」
夕焼けの日光を浴びながら、平山さんがブラックコーヒーを差し出してきた。
「ありがとうございます」
ヘルメットを外してプルタブを開けると、彼が
「どうしました? 目、赤いですよ」
と愚直に聞いてきたので、俺は「はは」と流してコーヒーを飲んだ。
俺は、ちょっとだけ優しい気分になっていたので、
「実はね、俺この学校の卒業生なんですよ。もう、あんまり覚えてないんですけどね。自分が通ってた学校を壊すのって、やっぱり、」
「勇気いりますよ」
と話してみた。
平山さんはまた
「そうですか」
と一言言って、
「私も、はい、卒業生です。ここの」
とだけ呟いて、歩いて行った。
その日の作業はそれで終わった。
おわり