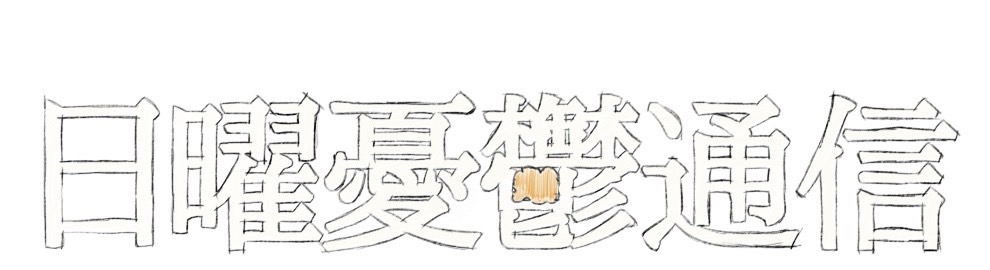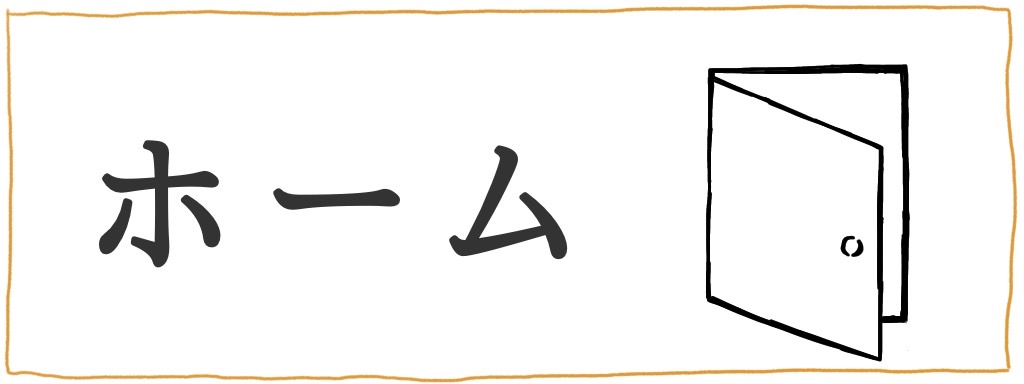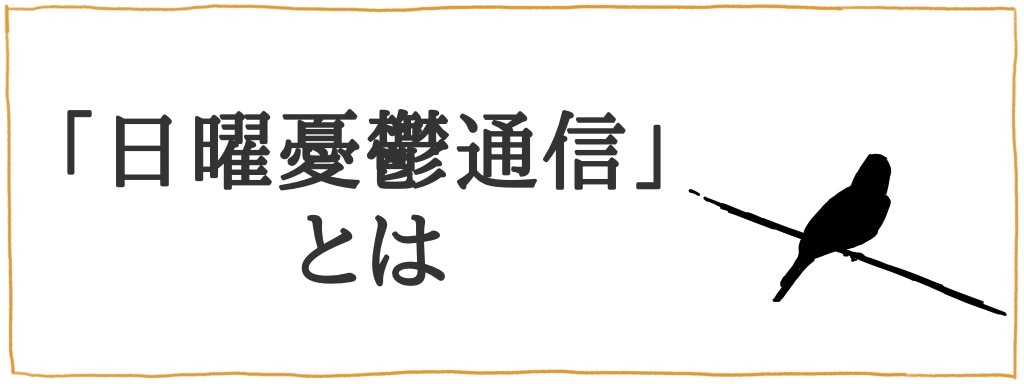私は幼少期のことをあまり覚えていません。
小学校に入学するより前の出来事なんて、印象にのこった記憶が断片的に残っているだけ。死海文書のようにバラバラな記憶で、時系列なんてもう滅茶苦茶です。必死に育ててくれた親には申し訳ないのですが、幼い頃の記憶なんてそんなもんです。親も当時の記憶を忘れてしまえば良いのですが、覚えているのだから厄介です。
「覚えてる? あんたは小さいときねェ……」
という前置きのあと、自尊心を持った大人の私に幼少期の小っ恥ずかしいエピソードを喰らわすのが親です。親子間に存在する抗いようのない情報格差に気が遠くなります。親の前ではつねに情弱という、子の苦しい運命です。
親に限らず、名前も知らないような近所のおばちゃんが「おばちゃん、あなたのオムツとりかえたことあるんだよぉ」と教えてくれることもあります。大人って子供のことを本当に良く覚えているんだなァと感心するとともに、昔の自分はどれだけの人間にオムツを交換させたのだろうと申し訳なくなります。「オムツを交換した」ということは、彼らは「私の排泄物をチラ見した」ということとイコールです。そんなの、誰も得しないじゃないですか。
しかし、生まれてから今まで一日もサボることなく生きてきたのに、その記憶が今では失われているなんて不思議なもんです。万が一、両親に和室へ呼び出されて、
「いままで隠していたんだが、お前はアンドロイドなんだ……」
「脳のストレージを節約するために、幼少期の記憶量を制限していたの。ごめんね、ごめんねぇ……(すすり泣く)」
ということがあったとしても、私は「あぁ、そうだったのか」と合点がいく気がします。親がもつ生命倫理のユルさに対してキレるのはその後でしょう。
記憶が失われているというのは、本当は生きていたのに生きていなかった扱いされているようで損した気分です。タイムパフォーマンスを気にかけて映画を2倍速でみるような我々世代が、「生きてたのに覚えてませ~ん」なんて不始末に耐えられるはずがありません。出来れば覚えていたいもの。
そこで今回は、「自分がもつ一番古い記憶」を思い出してみます。
覚えているのはやはり、何か強く印象に残ったエピソードが多いです。それも、命の危険に関わるようなもの。
まずは、プールの思い出です。これはかなり古いという自信があります。
ある夏の日、私はまだ幼稚園に入園もしていないような時期だった気がしますが、母と一緒に近所の市民プールに出かけたことがあります。「近所の」といっても田舎なので、車で5分ほどかかる距離にあります。なので日常的にプールへ行くということはなく、母とプールへ行ったのもそれが最初で最後だったはずです。
それもそのはず。母は泳げません。私はプールへ行ったらはしゃぎますが、母は行っても別に楽しくはないのです。私が子供用の浅いプールに入っている間、母はプールサイドに座って文庫本を読んでいました。その佇まいはいかにも「連れてきてやったぞ感」があり、
「大人は大変だよなぁ。プールに特別興味があるわけではないのに子供を連れてきて、ムダに時間を潰さなきゃいけないんだから……」
と子供心に思った記憶があります。でも母は無類の本好きなので、丁度良く趣味の時間ができて良かったのかもしれません。プールサイドなんかで本を読んだらページが濡れやしないか、と当時の私は心配になったのですが、今では私も風呂に入りながら本を読む人間へと成長したあたり、これが遺伝というものなのでしょうか。
その時は、母がプールサイドに座って本を読み、私だけがプールで遊んでいる状況でした。他のお客さんは誰一人としていなくて、プールは「The Backrooms」のような不気味な雰囲気に包まれています。
実はこのとき、私はプールに入るのがほとんど初めてでした。泳ぐなんて芸当はできません。プールの縁につかまりながら、足を滑らせないようにひたすら歩くだけ。こんなリハビリみたいな事をして、一体なにが楽しかったのでしょうか。子供というのは、大人たちからみたら何が楽しいんだか分からないような遊びを繰り返してサルみたいにキャキャキャと笑うものですが、このプールの思い出に関しては当時の私も楽しくなかったと思います。プールサイドで小説を読みふける母を見て、
「これは果たして『プールで遊ぶ親子』と言っていいのか……?」
と自問自答した覚えがあります。浮き輪もボールも持ってきていないのです。なんと無計画な親子だ、と私は恥ずかしくなりましたが、他のお客さんがいなかったのが助かりました。私はプールを歩行することに専念したのです。
よちよちとペンギンのような足取りで歩いていると、恐れていた事態が起こりました。足を滑らせ、ドブンと水に浸かってしまったのです。
私は何が起こったのか分からず、それまで水の冷たさに慣れていなかった肩から上の部分が一気に冷たくなったことに驚きました。
私は完全に水中で仰向けになり、水の中から水面を見上げました。その光景は幻想的で、沢山の小さな泡が水面に向かって浮かび上がり、波の上で光を反射して揺れていて、まるで透明な桜の木を見上げているようでした。
しかし、それだけ泡が出ているということはそれだけ空気を吐き出しているということであり、私はしっかりと溺れていました。ちなみに、この時の私はゴーグルを着けていません。そのため水中の光景は裸眼で見たことになるのですが、今の私は水中で目を開けることなどできないのです。私が記憶する数少ない「退化」です。
さんざん水中で苦しんだあげく、自力で起き上がったのか、それとも母に助けられたのかは覚えていませんが、私は無事に立っていました。恐らく、母に助けられたのだと思います。そうでなかったら、母は溺れる息子を尻目に小説を読んでいたことになってしまいます。よっぽど面白い小説を読んでいたのか、はたまた不器用なスパルタ教育の一環だったのかのどちらかになるでしょうが、いずれにせよ悲しいです。ここは母が助けてくれたと信じることにしましょう。
人生で初めて「溺れる」という経験をした私は、「溺れるとまず鼻がやられる」ということを学びました。鼻に水が入り、信じられないくらい鼻の穴が痛んだのです。絶対に入ってはいけない「立入禁止ゾーン」に水が浸入し、脳全体に警報が鳴らされているような痛み。普段は鼻水がうっとおしいくらい利用している通路なはずなのに、それが水になっただけでこんな痛くなるなんて不思議なモンです。
プールの記憶は以上になります。命の危機に瀕した衝撃的なエピソードだったので、そりゃ脳も覚えてるわといった感じです。
もう1つ、このプールの記憶と同じくらい古いのではないかと思われる記憶があります。だがそれも、命の危機に瀕した思い出なのです。よくもまあ今の今まで生きてこれたものです。日本の福祉に感謝です。
その思い出というのは、階段から転げ落ちた思い出です。いかにも、ですね。
私が小学2年くらいの頃、実家が大規模なリフォームをして平屋になりました。その前は2階建てで、かなり急な階段があったのです。平屋にしたのは、老後のことを考えた親の賢明な選択といえましょう。
その階段から、私は転げ落ちたのでした。ただ覚えているのは「転げ落ちた」という記憶だけで、それに至る経緯やその後の対処などは全く記憶にないのです。覚えているのは本当に、「ズガガガガ」という雪崩のような効果音だけです。
後になって家族から話をきくと、どうやら階段の手前にはしっかりと柵が設けられており、幼い私が転げ落ちないように工夫がされていたようです。そんな家族の工夫を無駄にして、私は柵を乗り越え、転げ落ちたのです。同情のしようがない、クソガキ的犯行です。親は「なにしてんだあの息子は!」とやるせない気持ちになったに違いありません。私も私で、「せっかく作ってある柵を乗り越えて、私は何がしたかったのだろう……」と呆然としたことでしょう。
余談ですが、数年前に見たネット記事で「幼少期に頭を打った人は、絵を描くのが好きな人間になる」という記事がありました。私は現に、絵を描くのが好きです。姉も同じように幼いころに頭を打った経験があるようなのですが、めちゃくちゃ絵が上手いです。そう思うと、あの時に柵を乗り越えて頭を打った甲斐があったなぁと思います。治療にあたった親の前ではそんなこと言えませんが。
私が覚えている古い記憶は、このような命の危機に瀕した記憶ばかりです。危なっかしい経験ばかりですが、これらの苦い記憶があるおかげで、ある程度成長したころには危険を冒さない保守的な人間になりました。これが良いか悪いかは別として、とりあえず幼少期の記憶は残っていたということで、私の過ごした人生は無駄になっていなかったとホッとするばかりです。